アマンバイ移住地の歴史

アマンバイ移住地は、1956年5月23日CAFE(Campania Americana de Fomento Economico アメリカ経済振興会社)耕地のコロノ(契約雇用農)として38家族260名が移住したことに始まります。
CAFE耕地は、1953年にアメリカ人クラレンセ・E・ジョンソン総支配人に設立された、パラグアイで最初の企業的カフェ栽培で、一般には「ジョンソン耕地」とも呼ばれています。
ブラジルで働いていたジョンソン氏は、当時パラグアイでは当時カフェ産業育成のための保護政策が検討されていたこと、また、ブラジルに比べて土地代が安いということ着目して1953年に同社を立ち上げ、カフェ栽培の適地としてブラジル国境のアマンバイ県のペドロ・ファン・カバリェーロ市(以下PJC)を中心とした土地を選び、二年間をかけて約235,000haほどの土地を買収しました。なおこれは、神奈川県に相当する面積です。
このジョンソン耕地の構想は、単なるロッテ分譲だけでなく、入植以前にコーヒー園を完成させて渡すという条件で、あらゆる市街地としての環境を整備した一大プロジェクトとして世界中の資産家に呼びかけられました。日本人コロノは、このコーヒー園の管理のために募集されました。
ジョンソンはブラジルにおいて勤勉に働く日本人コロノの高い評価を知り、WCC世界教会協議会を通じ、日本人コロノの募集を強く希望していました。それを受けて、第2次までは日本海外協会連合会と日本国際基督教奉仕団の二本立てで移住者の募集がされました。自営農移住が主であるここパラグアイでは、唯一のコロノ移住です。

しかし、実際のコーヒー雇用農(コロノ)とは、ブラジルの奴隷解放によって、コーヒー農園の奴隷に代わるべきものとして導入されたもので、その労働条件や待遇は非常に厳しいものでした。監督の見張りがあり、各耕地の門に施錠されているなど、自由が拘束された状態でした。
なお、当時の契約条件によれば、コロノは一世帯あたりの契約基準(一人あたりおよそ3,000株程度)にそって既植のカフェの管理受け持ち、1株あたり年間2グアラニー(約6円)の手入れ賃と報償金、そして収穫歩合に応じた収益に加えて、間作や自由耕作地での収入を合せた形で生計を立てることになっていました。また、契約満了後は安価かつ長期支払いが可能な条件での土地分譲が可能であったため、将来の独立自営を目標とした人々が募集に応じ、1956年4月に、第一陣である38家族260名を乗せたあふりか丸が横浜を出港しました。
しかし当時のパラグアイには、海外移住を促進し、その斡旋と援助を行う日本海外協会連合会(以下、海協連)はもちろん、公使館すらなく、受入準備はほとんど出来ていませんでした。そのため、急遽海協連ブラジル・サンパウロ事務所が受入態勢の整備に奔走し、一月あまりという短い期間で準備を進めました。

一方、日本からの入植者はブラジル・サントス港に到着し、サントスからはソロカバナ・ノロエステ鉄道を、薪を焚いて走る蒸気機関車に乗って、その距離約1,300km、時間にして約120時間近くを費やして5月23日に、ポンタ・ポラン市に到着しました。なお、ポンタ・ポラン市はPJCと道路をはさんで国境を隔てたブラジル側の町で、両方の町への行き来は現在も自由に行われています。
しかしながら、CAFE会社側の受入態勢の整備は遅く、収容所(移住者が移住当初に住む施設の呼称)の建設が進んでいなく、殆どの移住者が倉庫で雑居生活を強いられることとなりました。住宅状況はその後さらに悪化し、入植年次が下がるに従い、会社からの住居提供がなくなり、材料だけが支給されるようになったため、移住者自身でランチョと呼ばれる仮小屋を作ることになりました。しかし、第5次にはその材料の確保すらも難しく、丸太や竹やヤシの木などで原始的な家を作ることになり、夢を持った移住生活の現実が戦前もしくはそれ以下の暮らしであることに、失望した移住者も少なくありませんでした。
加えて、ジョンソン耕地側の計画した住環境・食生活・教育などの生活環境も、日本人移住者にとっては、とても満足できるレベルではなかったため、移住者はまずその環境作りを進める必要がありました。その中で、CAFE会社側との折衝や会員同士の親睦のため、1956年には日本人会を設立し、1957年には日本語学校を開設しました。

日本人移住者の中にはカフェ栽培はもちろん、肉体労働自体も未経験という者もあり、当初は必ずしも期待したほどの成果が上がりませんでしたが、次第に日本人移住者の勤勉さと定着性の高さが評価され、その後も移住者の受入が続きました。しかし、その半面で会社の経営状態は悪化の一途をたどって行き、1959年の収穫後の11月に破産宣告を受け倒産しました。
破産の原因には、日本人移住者が入植する前年である1955年と、入植初年である56年の8月に連続して霜害が起き、80%以上のカフェの樹が枯死するという事態が起きたために、当初の営農および経営計画が成り立たなかったことがあげられています。1958年に最後の第8次移住者が到着する頃までには、既に経営は困難を極め、資金難による月給遅配、配給の減配などが相次いだため、1957年だけでも約40家族がブラジルへと活路を求めて逃れるなどして、破産前後には既に日本人移住者の約6割が退耕していました。
残った日本人入植者たちも、倒産以前から会社の先行きを危ぶみ、カピタンバード市(PJCからブラジル国境に沿って120kmほど南下した地点)近隣に適地調査が行われるなど、独立自営に向けての取り組みがなされていましたが、それまでの困窮した生活により営農資金に欠ける移住者がほとんどであたため、1957年に設立された日本公使館へ支援を求め、公使館では駐在員の派遣と共に、海外移住振興会社からの緊急融資援助を行いました。その後、債権委員会でジョンソン耕地側に対して凍結された手入れ賃と収穫歩合などの債権回収を交渉に当たりましたが、非常に難航し、最終的に回収できたのは3年後の1962年、わずか35%程度に過ぎませんでした。

移住者達は債権回収を待つだけでなく、お互いに調査費を出し合い新たな入植地調査を行い、1960年には、PJCから20~30km離れたところにあるサンハプタン地区、シリグエロ地区などに分散して再入植し、自営開拓を進めていきました。また、同年には連携を強めて、営農資金の融資をあおぐために、アマンバイ農業協同組合を発足させました。60年代後半には、南部の移住地の不振を受けて、イタプア県内からの転住者もあり、開拓が進められていきました。
その後1970年に電話が開通し、1972年に発電所が竣工し、市内の電化が行われ、1978年に上水道、そして1980年に下水道が整備されて、現在に至っています。
アマンバイ移住地における営農の推移
CAFE耕地時代においては、カフェ農園のコロノであったことから、当然のことながらカフェが基幹作物でした。そしてその間作と自給作物として大豆、小麦、マイス、陸稲、フェジョン、各種の野菜などが栽培されていました。

CAFE耕地の倒産後、独立自営が行われるようになっても、カフェを中心とした営農が進められていきました。カフェは霜害を受けて減収になる危険性はあるものの、市場性も高いカフェは、海外移住振興会社による唯一の融資対象作物であったからです。移住者達は原始林を切り開いてコーヒーの木が次々と植え付けていき、1965年にはアマンバイ農協にコーヒー乾燥工場を竣工しました。移住者の営農形態は、永年作であるカフェを植え付け、その間作と家畜の飼育および蔬菜栽培、果樹の導入によって補完的な収入を得る形が中心となりました。この間作には大豆、マイス、フェジョン(豆)陸稲、小麦の植付けが行われた他、トマトやスイカなどの蔬菜栽培も行われました。これらの蔬菜はブラジル側でも好評を博し、移住者の重要な現金収入源となっていました。

しかしその後、1966年8月6日に大規模な降霜があり、カフェ農園に大きな打撃を受けた多くの移住者達は、換金作物としてのトマトなど蔬菜栽培のほかに、果樹、畜産、養鶏などへ営農の転換が進められていきます。
1970年に入ると、更に営農形態が再検討され、果樹、台湾桐、養蜂が導入され、カフェと雑作という形態から、他の永年作として果樹、台湾桐に加えて雑作、そしてそれに養鶏や養豚、さらに養蜂や養魚を加えた多角的な営農形態への転換が図られましたが、カフェに代わる主要作物を失ったことで営農が安定せず、商業などに転換して市内へ出る移住者も多くなりました。

1972年にはブラ拓の指導を受けて養蚕も始められました。一方、永年作として栽培が盛んになっていた台湾桐は病害により期待されていたほどの収入をもたらすことなく衰退してしまいました。
その後1975年には再度大規模な降霜があり、それまでカフェの栽培を続けていた農家もほとんどがその栽培を断念し、脱農・商工業への転換が加速しました。その後の農業はカフェに代わり、雑作の大型機械化農業に転換され、現在の移住地における主要作物は大豆、小麦となっています。
※ここまでの歴史写真はアマンバイ移住地25周年誌「雄飛」より引用しました。
アマンバイ移住地の関連地図
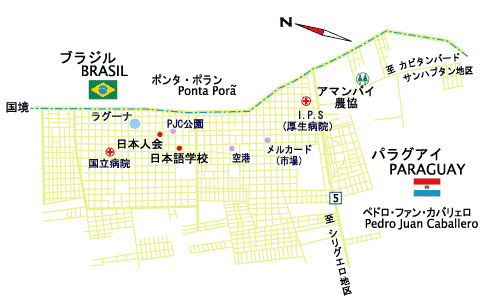
アマンバイ移住地の関連施設等
アマンバイ日本人会 公民館 1976年、入植20周年を記念して 建立された入植記念碑
カピタン・バードの日系社会と日本語学校

カピタン・バードとは、パラグアイ北部アマンバイ県都であるペドロ・フアン・カバジェロ(以下PJC)市からブラジル国境沿いに約120キロ南下した地点に位置する街で、道を隔ててブラジル側のコロネル・サプカイア市と隣り合う形になっています。
ここに日系社会が形成された経緯は、1956年にアマンバイ移住地ジョンソン耕地へコーヒー雇用農として入植した移住者によって始まっています。
日本人入植から僅か3年後の1959年にはジョンソン耕地が倒産し、その債権回収が思うように進まなかったため、入植者の中には離農して街で商売を始める者や、ブラジルへ転住する者が相次ぎました。その一方で農業を続ける移住者に対し、海外移住振興会社から土地20町歩分の購入資金の融資が行われたため、新たな入植地の調査も始められました。そうして再入植が進められたのが現在のサンハピタン地区やシリグエロ地区で、移住者達は自営農として開拓を進めていきました。
しかしながらこれらの地区では耕地の拡張には限界があったため、引き続き新たな耕地が調査されました。そして、候補に上がったのが現在のカピタン・バードです。当時、土地局につながりを持っていた奈良次郎兵衛氏によって、カピタン・バードにまとまった広さで購入可能な政府売り出し地があるという情報がもたらされた為、1963年には仙野一家がカピタン・バードへ入植したのがその始まりとなりました。その当時のことを仙野氏は、「家族が多かったこと、そして将来は牧場運営を計画していたので、より広い土地を求めて入植した。」と語っています。
仙野氏は入植してから薄荷や養豚、コーヒーの栽培などを手がけ、中でも薄荷はブラジルの三倍の売値がついたこともあり、敷地内に蒸留設備を設けて積極的にその生産を進めていました。しかし、その後70年代にアジアで薄荷の生産が始まるとそれほどの高値がつかなくなってしまったため、台湾桐の栽培にも着手しました。しかしこれも思ったほどの値がつかないことや、交通不便なカピタン・バードでは出荷がスムーズに行われず集積時に虫害が出るなどの障害があったため思ったほどは伸びず、80年代からは大豆作に転換しています。
仙野氏が入植した後、追ってブラジルの日系人の入植が始まりました。その背景としては、パラグアイはブラジルに比べ土地が安価であったこと、そして税金が安く、まだ土地に余裕があるという情報が流れたことによります。特に土地価格に関しては、「パラグアイなら、ブラジルで1haを購入する金額で100haが購入できる」とまで言われていました。
日本人会と日本語学校の歴史

こうしてブラジル・パラグアイからの入植者によって、1972年に親睦団体として日本人会が結成されました。創立時の会員数は7家族です。ブラジルからの移住者には、ブラジルから見ても奥地であるこの地区へ新天地を求めに来ただけあってどこか「一匹狼」的な気風が強くその組織作りは容易ではなかったとも言われ、その後自然消滅に至っています。
しかし、その後1987年になると、日本政府の無償援助による電化工事が企画されたことをきっかけに、日本人会が再結成されました。「日本人だけではなく、この地域全体を良くしていくために協力しよう」という言葉の元に寄付を募るなどの活動が行われ、電化工事が始まった1989年には23家族を数えるようになりました。その後電化工事が完成する1994年までの間にその会員数は増え続け37家族を数えるようになりましたが、この電化工事が完了するとまた次第に会員数は減少していきました。なお現在は、アマンバイ日本人会のカピタン・バード支部という位置付けとなっています。
一方で、この時期に集まった寄付の残金を利用し、1994年には日本語学校用地の購入がなされました。それまでは数人の移住者宅で私塾的にされていたのですが、1994年からはその敷地の倉庫を利用した形での学校が始まりました。その後1999年には日本大使館の草の根無償援助を受け、2000年には用地に現在のカピタン・バード日本語学校が建設されるに至っています。
カピタン・バード日本語学校にみるカピタン・バード日系社会の特異性

ブラジルから転住してきた移住者の多くは二世の世代だったこともあり、現在カピタン・バードに住む日系人のほとんどがポルトガル語を母語とし、日本語を話す日系人は非常に限定されており、日系世帯数は数世帯に過ぎません。よってこの日本語学校生徒も、その8割が非日系(パラグアイ人、ブラジル人)です。彼らの学習動機は様々ですが、親が日系移住者を通じて知った日本文化や日本という国に興味を持って自分の子どもを通わせたり、生徒自身がアニメやゲーム、テレビなどをきっかけに日本に興味を持ったりすることなどが挙げられています。また、このカピタン・バード地区そのものが、1989年から1994年の電化工事、1994年の消防車寄贈と日本からの支援を多く受けているため、日本と日本人に対する信頼は深く、その言語である日本語に対する興味を生みだす土壌となっています。
これを受けてカピタン・バード支部では、地域の子供たちがこの日本語学校で学ぶことを通して日本人の持つ良い習慣や考え方など身に付けるようになることが、人間性そのものの教育に役に立つことであると考えて、非日系・日系を問わずその門戸を開放しています。他のパラグアイの日系移住地および日系社会では、継承語としての日本語教育から始まり、また現在もそれが日本語学校の主流であるのに比べると、カピタン・バード日本語学校の位置付けは非常に特異です。
また、少人数組織である為、その学校運営資金のために日本人会支部としては毎週水曜日、日本語学校としても毎週金曜日にはブラジル側で行われるフェリア(市場)に出店し、その運営資金の調達に努めています。これも、日系社会という枠を超えた地域全体で学校を支えていくという形としては、他のパラグアイの日系移住地・日系社会には見られないことです。
現在もカピタン・バードへはPJCからの舗装道路が敷設されておらず土道のみ(パラグアイ側。ブラジル側には舗装道路がある)のため、車であっても約3時間程を要し、悪天候時はぬかるみがひどくなり定期バスの運行が不可能になることもあります。このような交通の不便さ、そして他の日系移住地との成り立ち・構成員の差から、それまでは必ずしも他のパラグアイの日本語学校との情報共有が図れてはいなかった側面がありますが、今後は連合会や全パラグアイ日系人教育推進委員会を通し、全パラグアイの日系社会に対して、将来の日本語学校の一つのモデルを示していく可能性があると言えるでしょう。
取材協力:アマンバイ日本人会カピタン・バード支部支部長 鈴木セルヒオゆきおさん
元カピタン・バード日本人会会長 仙野金雄さん
日系社会青年ボランティア17回生羽田野香里さん
参考資料:「カピタン・バード日系社会の歴史と学校」(日系社会シニア・ボランティア村上忠三郎先生)1999年度研究集禄(アマンバイ日本語学校)
参考文献
アマンバイ移住地25周年誌「雄飛」(アマンバイ移住地25周年誌刊行委員会)
パラグアイ日本人移住50年史「栄光への礎」(パラグアイ日本人会連合会)
「アマンバイ移住地呼び寄せの父」ジョンソンとジョンソン耕地(青山千秋)
取材および撮影等協力
アマンバイ日本人会
アマンバイ農業協同組合
加藤敦司さん(日系社会青年ボランティア17回生・アマンバイ農業協同組合)







